祖父が亡くなって一年経った。
大切な人がこの世にいなくなっても、生活は続く。いつまでもさめざめと泣いていては暮らしていけない。四六時中祖父のことを考えているわけでもない。大好きな人ともう2度と会えなくても私は子供を育てないといけないし、霜降り明星のラジオを聴いたら笑うし、リンツのチョコを食べたら美味しいと思う。そうやって日々を生きている。
けれど悲しみは、今もふとしたときに顔を出す。その心の痛みを感じるとき、私は少しホッとする。まだ私の中で、気持ちが死んでないことを確認できるから。
祖父の火葬後、骨を箸で拾う所謂「骨上げ」をしたとき、白い骨に混じって幾つかの部位がピンク色になっていた。ちょうどこんな朝焼けの空のような、淡い桜色。

それを見て、火葬場の職員のかたが「花びらの色がお骨に移ったら、こんな色になるのですよ」と教えてくれた。
その時は、片方長さの違う箸(骨上げの時は箸の長さをわざとちぐはぐにするそうだ)を持たされた我々は一同に「そうなんですねえ」と頷いたが、今思うとあれは嘘だ。
だって、3時間以上かけて1000度もの熱で焼かれるんだよ。分厚い肉が跡形もなくなるのに、小さな花の組織なんか残るはずないじゃないか。あれは、肉と骨が焼かれた色なんだろう。でもそんなことをいうと生々しいので、この場では花の色と説明することになっているのだろう。
だけどそのとき、家族の誰もが花の色だという説明に納得してしまう理由もあった。
以前ブログにも書いたが、祖父の棺には、私が今まで行ったどのお葬式よりも、可愛らしく、美しい花がどっさりと供えられていたのである。よくある菊の花ではなく、まるで結婚式のブーケのような楽しげで可憐な花束を、溢れそうなほど祖父のまわりに散りばめた。それは、生前祖父をよく知る花屋さんの意向だった。おじいちゃんは、ほんとうに友達が多かった。葬儀屋から花屋、住職、全員祖父のとこをよく知る人で、心からの言葉をかけてくださった。私が見たほとんどの葬式は「そういう仕事の人がそういう仕事だからやる」以上の言葉も花もなかったし、そのことを悪いと言うつもりもないしそれが普通だと思う。
花の色がお骨に移ってピンクになる、というのは、世の中数多ある嘘の中でもとても優しい部類の嘘だ。
私の母は、「亡くなった人を想うとき、天国でその人の上に花が降る」といった。あれも嘘だ。でもそれも、無いよりあるほうがずっと良い、素敵な嘘だ。
最近私はこの本を買った。いくつかの「さよなら」をまだ心に引きずりながら生きる私にはとても惹かれるタイトルだったから。
この本には、日本人と「さよなら」の関係、そして死についての考察が、実に様々な古典・現代文学や哲学、宗教などの文献を用いて書かれている。それだけでもかなり読みごたえがある。
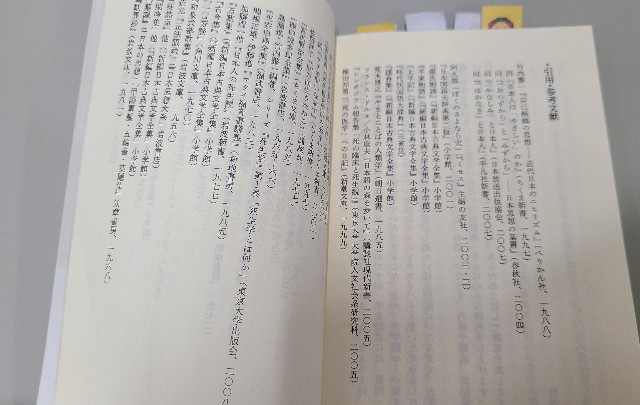
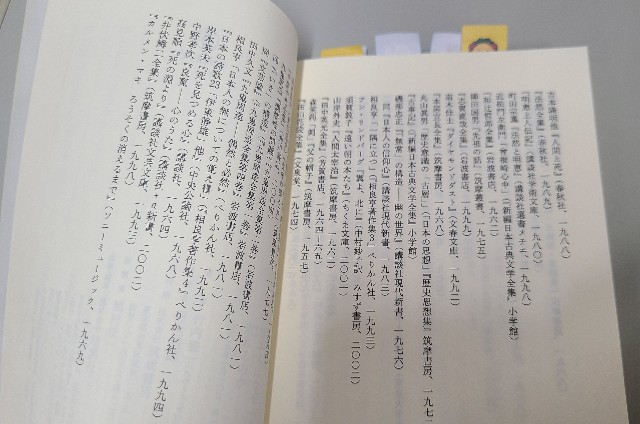
世界の別れの言葉は「神のご加護を祈る」「またあいましょう」「お元気で」というパターンに分類されるという。しかし日本語の「さよなら」はどのパターンにも当てはまらない。「さよなら」は、「左様であるならば」つまり、接続詞を別れの挨拶としているのだ。アメリカの紀行作家アンリンドバーグの文章がとても良かったので引用する。
「サヨナラ」を文字どおりに訳すと、「そうならなければならないなら」という意味だという。
これまでに耳にした別れの言葉のうちで、このように美しい言葉をわたしは知らない。
〈Auf Wiedersehen〉や〈Au revoir〉や〈Till we meet again〉のように、別れの痛みを再会の希望によって紛らわそうという試みを「サヨナラ」はしない。
目をしばたたいて涙を健気に抑えて告げる〈Farewell〉のように、別離の苦い味わいを避けてもいない。
……けれども「サヨナラ」は言いすぎもしなければ、言い足りなくもない。
それは事実をあるがままに受け入れている。
人生の理解のすべてがその四音のうちにこもっている。
ひそかにくすぶっているものを含めて、すべての感情がそのうちに埋み火のようにこもっているが、それ自体は何も語らない。言葉にしないGood-byeであり、心を込めて握る暖かさなのだ――「サヨナラ」は。AnneMorrowLindbergh(著)、中村妙子(訳)『翼よ、北に』
私は自分がさよならを言う時、正直ここまで考えていなかった。こういう視点があるのは、世界中を飛び回っていたアンリンドバーグならではの着眼点なのかもしれないけれど、もともと感性が研ぎ澄まされた人物だったのだろうなと思う。だって世界各国を旅したり言葉を多く知っている人全員がこんなふうに物事を捉えているとは思えない。そのぐらい素敵な着眼点だと思った。
昔から日本人の考え方の根底には、死を劇的な扱いにせず、今日の延長にあるものとしての捉え方があった。今日をより良く生きようとすることが、すなわち良い明日へ繋がる。明日のために今日を蔑ろにするでもなく、明日を投げうって今日の刹那的な快楽にふけるでもなく、後悔のない今日を生きることが大切なのだ。
……というようなことが全体を通して書かれていたと思う。全然違ったらどうしよう。とにかく良い本だった。だけど、これを読んだからって、悲しみから一気に解放され救われました!っていうものでもなかった。ただ、死があって、そして「左様であるならば」と今日があり、明日があり、かつて大好きな人がいた日々と、いまを「接続」してる言葉。それがさよなら。
途切れるものではない、そう思うだけで、なんだか少し寂しさが和ぐ気がした。
